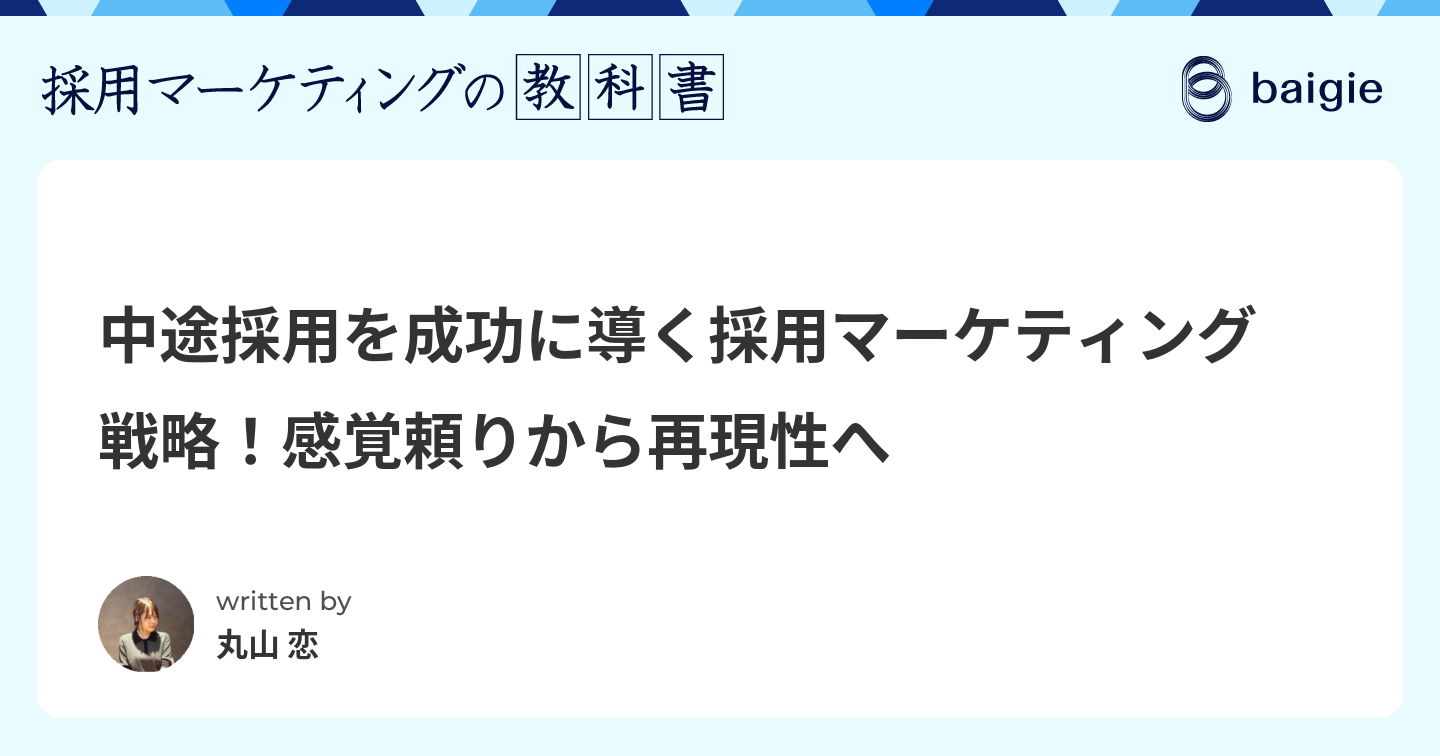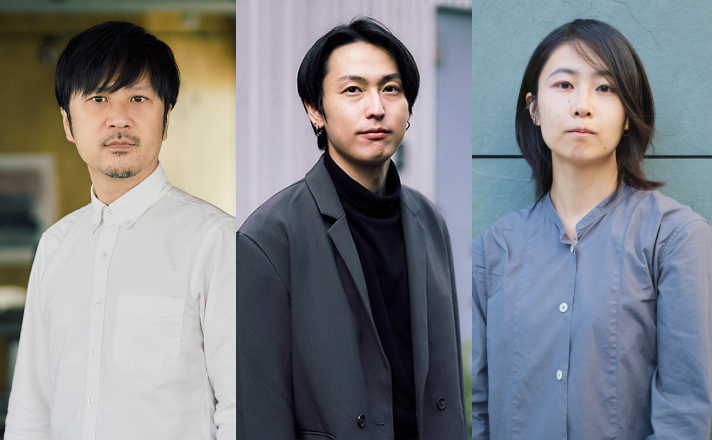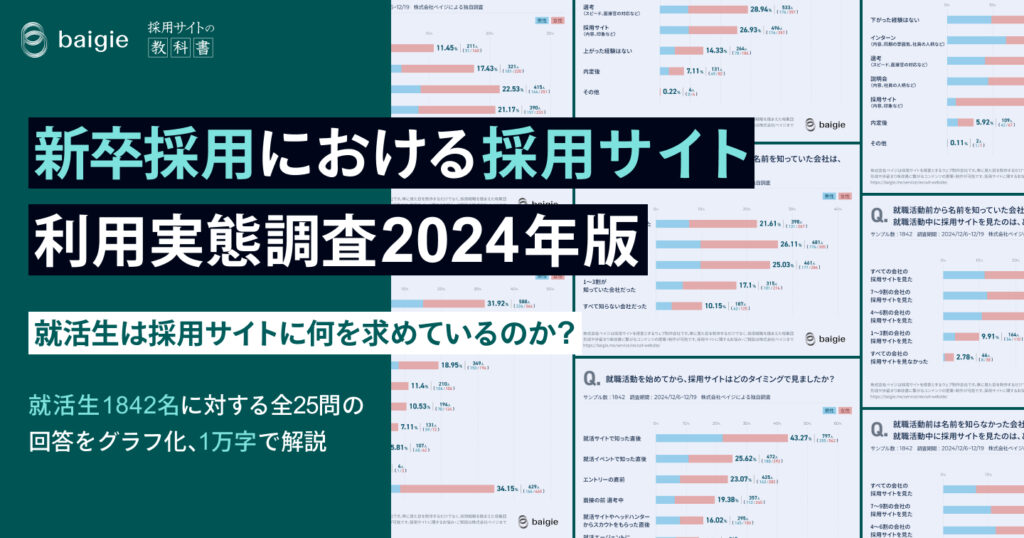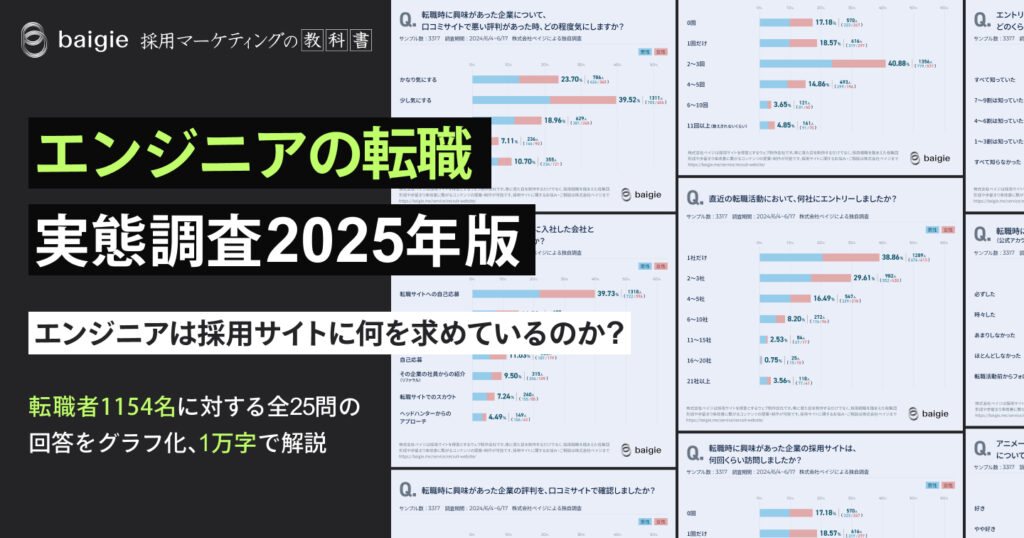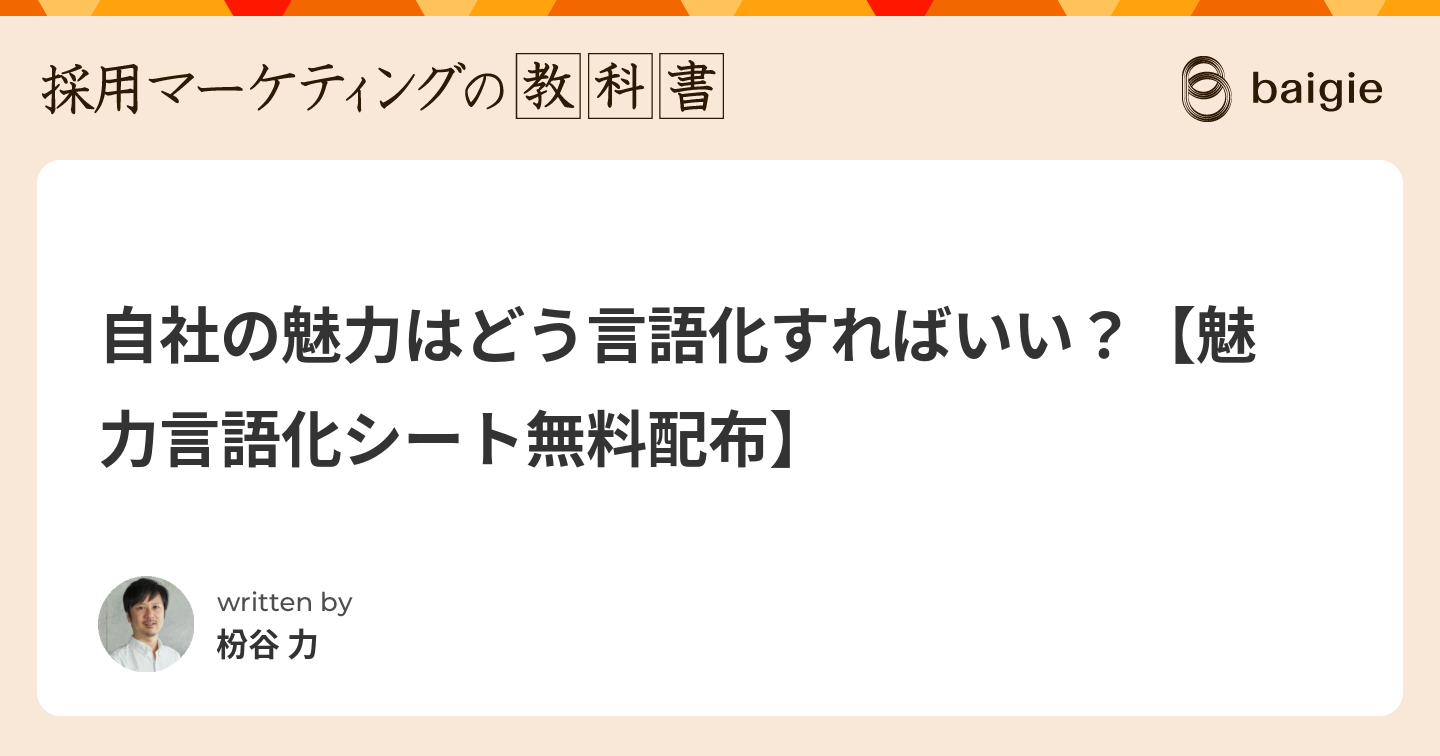中途採用を担当する人事・採用担当者の方は、業務に追われる日々の中で、
「自社にマッチする人材の応募がこない」
「早期離職が起こってしまう」
「競合に優秀な人材が流れてしまう」
といった課題に悩んでいませんか。さらに、その対策として新しい手法やツールを試しても、思うように効果がでない。と感じている方も多いのではないでしょうか。
その原因は、表面的な施策だけに振り回されてしまう、戦略の欠如にあるかもしれません。中途採用を成功させるには、「転職市場の動向」「自社の真の価値」そして「求職者が何を求めているか」という根本的な問いに向き合うことが不可欠です。
これらの課題を解決するための体系的なアプローチ、それこそが、今回ご紹介する「採用マーケティング」です。
本記事では、中途採用を成功に導く「採用マーケティング」の考え方と実践ステップを、重要なポイントやメリットとともにわかりやすく解説します。再現性の高い仕組みを取り入れ、中途採用を成功させましょう。
採用マーケティングとは?定義と3つの重要な考え方
「採用マーケティング」とは、言葉の通り、採用活動にマーケティングの考え方を応用したものです。ただし、ここでいう「マーケティング」とは、ただ単に「宣伝」「販促」「数字管理」のように、市場との接点を、一部だけ切り取ったようなものではなく、市場に対して働きかけるすべての活動を包括したものを意味します。
採用マーケティングの定義
採用マーケティングとは、「採用市場における自社と求職者の関係性を最適化する体系的アプローチ」と定義できます。
これは、商品やサービスを顧客に届けるマーケティングと同様に、「誰に(求職者)」「何を(自社の魅力)」「どのように(手法)」伝えるかを戦略的に設計し、実行していくプロセスです。
単発の求人掲載やスカウトメールの送信といった個別のアクションではなく、採用活動全体を一つのプロジェクトとして捉えることで、一貫した戦略のもとで施策を実行することができます。
採用マーケティングで重要な3つの考え方
採用マーケティングを実践する上で、特に重要な3つの考え方があります。
1. 求職者起点(顧客起点)の思考
これはマーケティングの根幹であり、採用においては「求職者の視点に立つこと」を意味します。企業側の「こんな人材が欲しい」という都合だけでなく、「求職者は何に不満を感じ、何を求めているのか?」という視点で、採用活動のすべてを設計します。
求職者が本当に知りたい情報(仕事内容、社風、人間関係、キャリアパスなど)を公開し、彼らの不安を解消するようなコミュニケーションを心がけることが不可欠です。
2. 目的志向の思考
採用活動の真の目的は、単に「応募数を増やすこと」や「内定者を出すこと」ではありません。「入社した人が活躍し、長く働いてくれること」が最終的なゴールです。この目的を常に念頭に置くことで、短期的な効果を追い求めるのではなく、ミスマッチを防ぐための情報提供や、長期的な関係構築を重視した活動が可能になります。
3. データドリブンな思考
「感覚」や「経験」に頼るのではなく、データを活用して定量的な判断をする考え方です。Webサイトのアクセス解析、応募者の属性データ、面接の通過率、内定辞退率などを分析し、課題を特定します。これにより、「なぜ応募が来ないのか?」「なぜ内定辞退が増えているのか?」といった根本的な原因を突き止め、効果的な改善策を打つことができます。
中途採用における採用マーケティングとは?新卒採用との違いも解説
採用マーケティングの考え方は、新卒採用と中途採用のどちらにも有効です。しかし、ターゲットや市場の特性が異なるため、それぞれに合わせたアプローチが求められます。
中途採用に採用マーケティングが不可欠な理由
中途採用市場は、新卒市場とはいくつかの点で大きく異なります。
- ターゲット層の多様性:
職種やスキル、経験、転職の目的が多岐にわたるため、画一的なメッセージでは響きません。ひとつの職種であっても、求職者が求める条件は人それぞれ異なります。
求職者は、自分の価値観と照らし合わせて判断をするため、目指す姿(顧客性との関係性を築く・年収〇〇超えを目指す・切磋琢磨して成長するなど)に合致した訴求や、避けたい状況(ノルマに追われたくない・プライベートを犠牲にしたくない・市場価値をさげたくないなど)に合致した情報公開がなければ、不安要素が残って応募まで踏み切れません。
- 転職潜在層の存在:
積極的に転職活動をしていないが、よい機会があれば転職を考える「潜在層」が多数を占めます。彼らに接触し、興味を持ってもらうための継続的な情報発信が必要です。
東日本大震災や、コロナ禍、エンタメ業界の権威崩壊などを目の当たりにしてきた若い世代は、「約束された安定はない」「少し先はどうなるかわからない」という価値観を持つ傾向があります。
そのため、就職においても、終身雇用や昇進ステップなど、会社の状況に依存した安定を疑い、自分自身が環境を変えることで解決する人が増えています。結果、積極的に転職活動をしている人以外の「潜在層」も、採用活動においては考慮が必要です。
- 即戦力への期待:
企業は即戦力となる人材を求めており、求職者も自身のキャリアアップやスキルアップを重視します。
近年の求職者は、自分のキャリアを「所属している企業」だけでは考えていません。どんなキャリアを歩んできたか、どんな選択をしてきたか、どんな結果を残してきたか、などをすべて含んだ「キャリアの変遷」で捉えています。
募集している役割について、単なるポストではなく「そこでどんなストーリーが期待できるのか」を合わせて伝えなければなりません。
このような中途採用市場の特性に対応するためには、一人ひとりのニーズを深く理解し、長期的な関係性を築いていく採用マーケティングの考え方が不可欠なのです。
新卒採用とのアプローチの違い
新卒採用は、特定の時期に、多くの学生に向けて一斉にアプローチする「イベント型」の要素が強いです。一方、中途採用は、年間を通して特定のスキルを持つ人材にピンポイントでアプローチする「通年型・個別最適型」の要素が強く出ます。
さらに新卒採用では、入社後の教育やポテンシャルを重視する傾向がありますが、中途採用では「職務内容」や「スキル」に加えて、「なぜこの会社でなければならないのか?」という、より具体的な動機付け(転職理由やキャリアの展望)が重要になります。
そのため、中途採用における採用マーケティングでは、ターゲットのセグメントを細かく設定し、一人ひとりの課題やキャリア観に合わせた情報提供を行うことが成功の鍵となります。
中途採用で採用マーケティングをする5つのメリット
採用マーケティングを実践することで、中途採用は以下のような5つのメリットを得られます。
- 応募数の増加と質の向上
- 採用コストの削減
- 属人化を卒業し再現性を高める
- 採用ミスマッチの防止
- 企業のブランド力向上
1. 応募数の増加と質の向上
求職者起点で自社の魅力を発信することで、自社に興味を持つ母集団を形成できます。さらに、ターゲットを明確にしてメッセージを最適化することで、単なる応募数だけでなく、自社にマッチした質の高い応募が増加します。
2. 採用コストの削減
効果の低い媒体への依存を減らし、自社のオウンドメディアやSNSなどを活用することで、広告費や紹介手数料といった採用コストを削減できます。また、質の高い応募が増えることで、選考にかかる時間や労力も削減され、総合的なコスト効率が向上します。
3. 属人化を卒業し再現性を高める
データに基づいた戦略を立て、プロセスを明確にすることで、特定の担当者の経験や勘に頼る「属人化」を防ぎます。成功した施策を分析し、そのノウハウをチーム全体で共有することで、誰が担当しても成果を出せる再現性の高い採用活動を構築できます。
4. 採用ミスマッチの防止
求職者が本当に知りたい情報を積極的に開示することで、入社後のギャップを減らせます。たとえば、会社のよい面だけでなく、課題やこれから取り組むべきことも正直に伝えることで、入社後の早期離職を防ぎ、エンゲージメントの高い社員を増やすことにつながります。
5. 企業のブランド力向上(採用ブランディング)
採用マーケティングを通じて、一貫したメッセージを社会に発信し続けることは、採用ブランディングの構築につながります。企業としての魅力や価値観が広く認知されることで、優秀な人材が集まりやすい土壌を築くことができ、中長期的な採用競争力を高められます。
中途採用で採用マーケティングを実践する8つのステップ
実際に中途採用での採用マーケティングを始めるには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここでは、中途採用で採用マーケティングを成功させるための具体的な8つのステップを紹介します。
ステップ1:採用課題の特定とKGI/KPIの設定
まずは、自社の採用活動における課題を特定します。
「応募数が少ない」「書類通過率が低い」「内定辞退が多い」など、どこにボトルネックがあるのかを明確にしましょう。
次に、その課題を解決するためのKGI(最終目標)とKPI(中間目標)を設定します。
- KGIの例: 優秀なエンジニアを年内に5名採用する
- KPIの例: 応募者数を月50名にする、スカウト返信率を10%に改善する、内定承諾率を80%に向上させる
ステップ2:ターゲット人材の明確化(ペルソナ設定)
KGIを達成するために、どのような人材を採用すべきかを具体的に定義します。
単に「営業経験者」と定めるのではなく、年齢、職務経験、スキル、性格、価値観、転職理由、情報収集の方法など、架空の人物像(採用ペルソナ)を詳細に設定することで、メッセージの方向性が定まります。
採用ペルソナを設定する際は、自社で活躍する社員を参考にするのもよいでしょう。ただし、数が多いとぶれてしまうため、基本的には3、4人程度にしておきましょう。
ステップ3:自社の魅力の言語化(EVPの策定)
次に、設定したペルソナが「この会社で働きたい」と感じるような、自社独自の魅力を言語化します。
- どんな仕事ができるか?(仕事のやりがい)
- どんな人が働いているか?(組織文化、人間関係)
- どんな成長機会があるか?(キャリアパス)
- どんな待遇・制度があるか?(給与、福利厚生、働き方)
これらを整理し、競合他社にはないユニークな価値(EVP:Employee Value Proposition)を策定します。働いている人の価値観によって、複数の個別の価値が存在するため、社員アンケートを実施するなどして、できるだけ多くの情報を収集するとよいでしょう。
ステップ4:情報発信チャネルの選定
ペルソナがどこで情報収集しているかを分析し、最も効果的な情報発信チャネルを選定します。
求人媒体、転職エージェント、ダイレクトリクルーティング、SNS(X、Facebookなど)、自社採用サイト、オウンドメディアなど、複数のチャネルを組み合わせることが一般的です。求職者がその情報にたどり着くまでの流れや、その後の反響も想定して選びましょう。
ステップ5:コンテンツの企画・制作
ステップ2で設定したペルソナの心に響くコンテンツを企画・制作します。
- 求人票: 仕事の魅力が伝わるように職務内容を具体的に記載する。
- 採用サイト: 企業の雰囲気や社員のインタビュー記事などを掲載する。
- ブログ・オウンドメディア: 会社の技術や文化、働き方に関する記事を発信する。
- SNS: 日常のオフィス風景やイベントの様子を投稿する。
ひとつのコンテンツに情報を詰め込みすぎないよう、コンテンツの役割を「知る→興味を持つ→応募する」という求職者の行動フェーズに合わせて作り分けることが重要です。
ステップ6:求職者との関係構築(ナーチャリング)
応募に至る前の「転職潜在層」に対して、継続的に情報を提供し、自社への興味を高めてもらう活動を、ナーチャリングと呼びます。
- メルマガ: 企業ブログの更新情報を定期的に配信する。
- イベント: カジュアル面談やミートアップを開催し、直接対話する機会を設ける。
- SNS: 企業アカウントから役立つ情報を発信する。
ステップ7:採用プロセス(選考体験)の最適化
応募後の選考プロセスも重要なマーケティング活動です。
求職者が「この会社は丁寧に対応してくれる」と感じるような、質の高い選考体験を提供することで、たとえ不採用になってもよい印象を持ってもらえます。これは、将来の応募につながるだけでなく、企業の評判向上にもつながります。
ステップ8:効果測定と改善
実行した施策の成果をデータで測定し、PDCAサイクルを回します。
「どのチャネルからの応募が多かったか?」「どのコンテンツが応募につながったか?」などを分析し、次のアクションに活かしましょう。この継続的な改善こそが、採用マーケティングを成功させる上で最も重要なポイントです。
データの計測は、GoogleのスプレッドシートやExcelにまとめてもよいですし、HRMOS採用やHERP Hireのような、採用活動に特化したツールを導入してもよいでしょう。
採用マーケティングで使えるツール・プラットフォーム5種
採用マーケティングを効率的に進めるには、適切なツールやプラットフォームの活用が不可欠です。
- 採用管理システム(ATS)
応募者情報の一元管理、進捗管理、選考状況の可視化を可能にします。たとえば、HRMOS・面接コボット・Findinなど、複数あるため、自社がすでに使用しているものとの相性や機能性で選びましょう。
- ダイレクトリクルーティングツール
企業の求める人材を能動的に探し、スカウトを送るツールです。BizReach・Wantedly・Green・エン転職ダイレクトなどがあります。それぞれに登録ユーザーの傾向、得意業界や得意業種があるため、目的に応じて選びましょう。
- SNS
企業の文化や日々の様子を発信し、潜在層との接点を作ります。X・Instagram・YouTube・TikTokなど、写真や映像なども活用して自社の魅力を伝えましょう。なお、利用する際には、炎上などのトラブルを避けるため、あらかじめルールを策定してから運用しましょう。
- 採用ブログ
企業の魅力を深く伝えるための、中心的な役割を担います。WordPressやStudioなどを利用するのもよいですし、誰でも簡単に投稿できるため、noteを利用する企業も増えています。
- Webサイト解析ツール
アクセス数やユーザーの行動を分析し、採用サイトの課題を特定します。Google Analytics 4・AI アナリスト・ミエルカアナリティクス・Similarwebなど、目的や用途に合わせて、使いやすいものを選びましょう。
中途採用マーケティングの成功パターン例
事例1:IT企業A社
- 課題: 従来の求人媒体では応募が集まらない。特にエンジニアの採用に苦戦。
- 施策:
- 採用ペルソナの設定: 他職種からエンジニアを個別化ターゲティング
- オウンドメディア運用: 自社ブログで技術的な記事や社内イベントの様子を公開。
- SNS活用: Twitterで社員が技術的な知見を発信。その企業の固定イメージにあてはまるものだけではなく、意外な一面も見せる。
- 選考体験の改善: 面接前にカジュアル面談を導入し、相互理解を深める機会を創出。
- 結果: 応募数が前年比で2倍に増加。特に、求人媒体経由では出会えなかった優秀なエンジニアとの接点が増え、内定承諾率も大幅に向上しました。
事例2:製造業B社
- 課題: 企業イメージが古く、若手人材の応募が少ない。
- 施策:
- 採用サイトのリニューアル: 専門用語を避け、若手にも伝わる言葉で会社の事業内容や魅力を再定義。若手社員の動画や写真を掲載し、若手でも活躍できるイメージを持ってもらう。
- 社員インタビューの充実: 職種や年齢の異なる社員の「リアルな声」を動画コンテンツとして公開。
- SNSでの情報発信: Instagramで工場の様子や社員のランチ風景などを定期的に投稿し、親しみやすさをアピール。
- 結果: 若手からの応募が急増。特に、動画コンテンツは求職者の不安を払拭する効果があり、選考中の辞退率が低下します。
さいごに:中途採用を成功させるために
中途採用における採用マーケティングは、単なる応募者数を増やすためのものではありません。それは、「自社に本当にフィットする人材を、継続的に獲得し、長く活躍してもらう」ための戦略的な取り組みです。
この戦略を成功させる鍵は、採用市場全体を俯瞰し、設定した目標に向かって一歩ずつ着実に進むことです。そして、何より重要なことは、「求職者の視点」を徹底的に持つことです。
この記事でご紹介したステップとツールをぜひ活用し、御社ならではの採用マーケティングを実践してみてください。きっと、今抱えている中途採用の課題を解決する糸口が見つかるはずです。
私たちは、採用人事戦略から共に考える
採用サイトに強いウェブ制作会社です
採用に精通したコンサルタントたちがお客さまの採用サイトの問題を解決します
こんな記事も読まれています