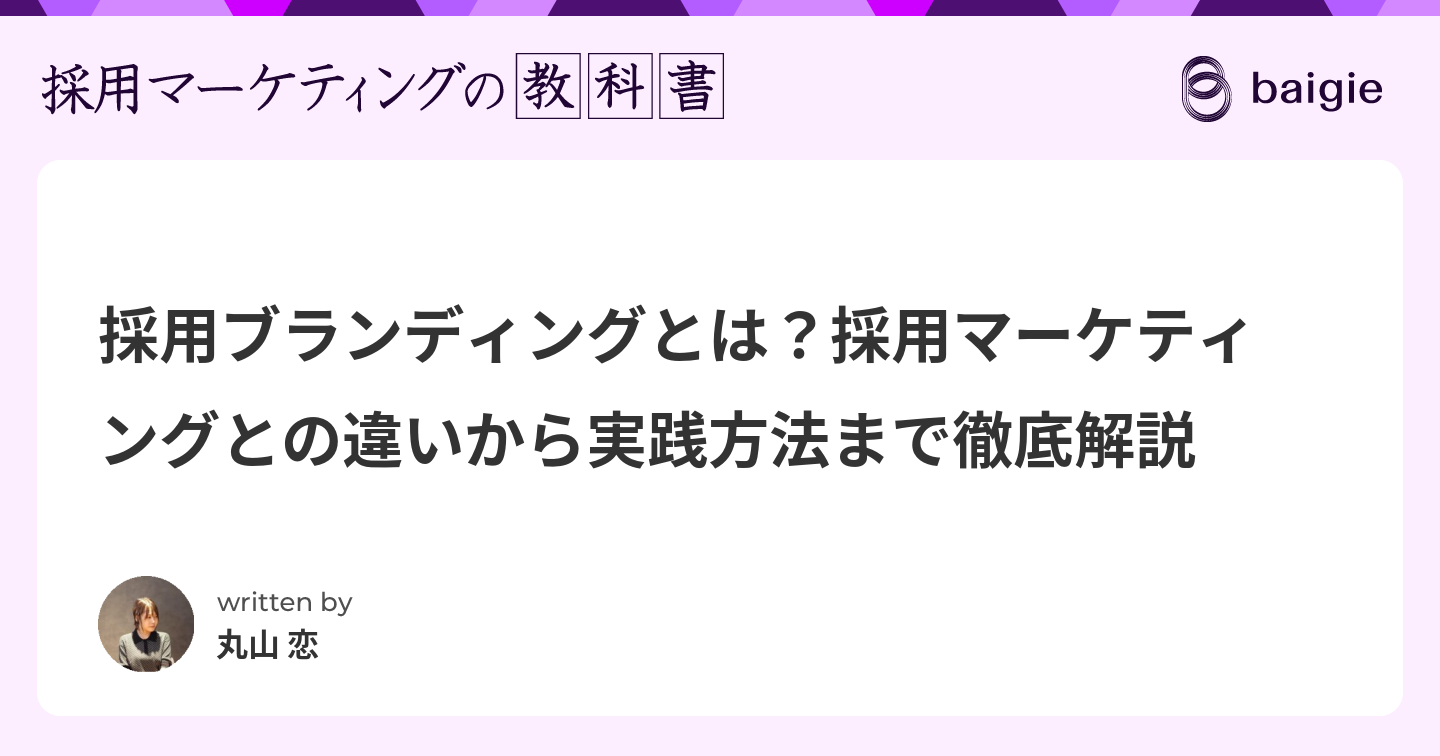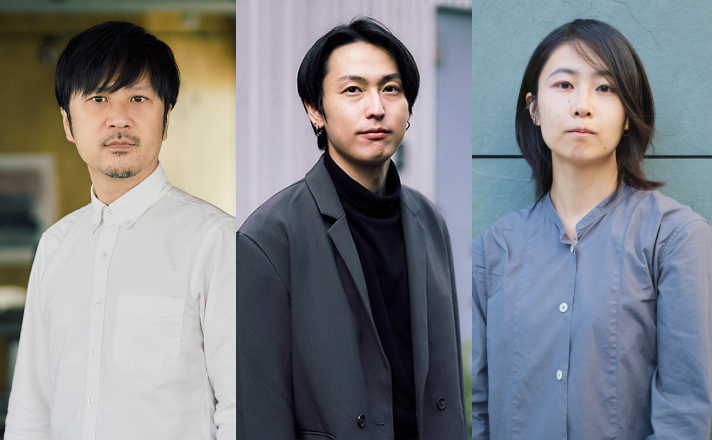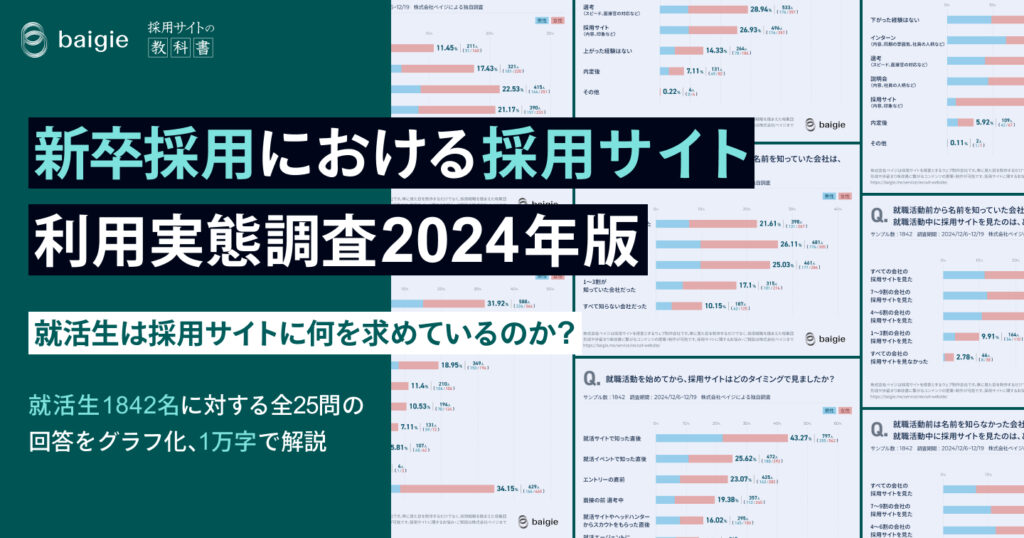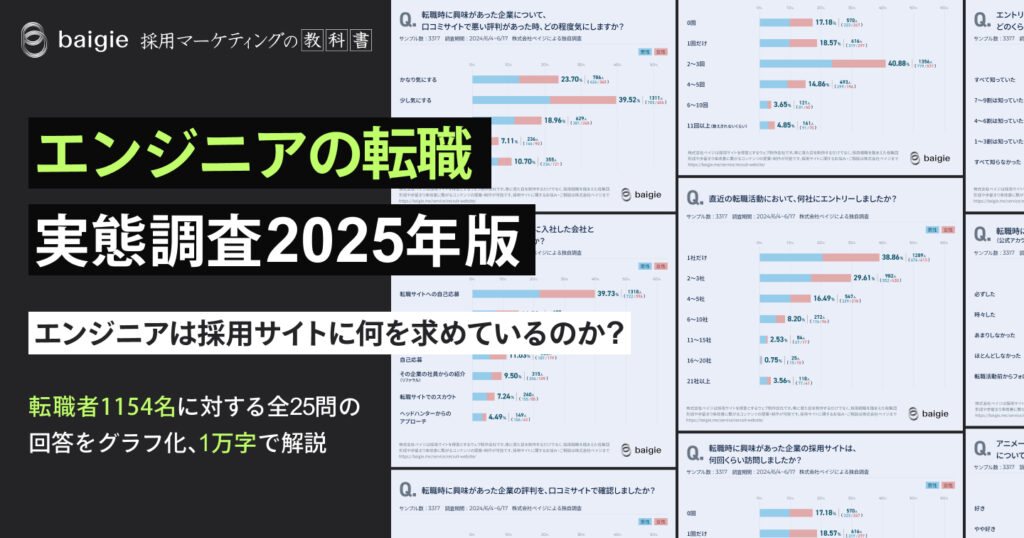「なぜあの企業には優秀な人材が集まるのだろう?」
こんな疑問を持ったことはありませんか?その答えのひとつが「採用ブランディング」かもしれません。
現在の労働市場では、企業が求職者を選ぶだけでなく、求職者も企業を選ぶ時代になりました。特に若い世代は、給与や待遇だけでなく、企業の価値観や働きがい、そして「その企業で働くことが自分にとってどんな意味を持つか」を重視しています。
本記事では、マーケティング理論をベースに、採用ブランディングを体系的に解説します。具体的なアクションプランもチェックリスト形式でご紹介しますので、実務にお役立てください。
採用ブランディングとは?
採用ブランディングとは、求職者に「この企業で働きたい」と思ってもらうために、自社の魅力を明確にし、効果的に伝える活動全般を指します。
単に求人情報を発信するだけでなく、企業理念、文化、働く環境といった自社ならではの価値を整理・表現し、求職者に対するあらゆるコミュニケーションで一貫させます。これは、消費者に商品を選んでもらうためのブランドづくりをするように、求職者に就職先として自社を選んでもらうための「採用ブランド」を作る取り組みです。
採用ブランドを確立することで、競合他社と差別化された独自の魅力を覚えてもらえるようになり、結果として優秀な人材の獲得と、入社後の高い定着率につながります。
採用マーケティングとの違い
採用ブランディングは、しばしば採用マーケティングと混同されますが、採用マーケティングの一部として位置づけられることが多い概念です。
採用マーケティングは、採用市場に対する働きかけ全般を指し、その中で「誰に(求職者)」「何を(自社の魅力)」「どのように(手法)」伝えるかを戦略的に設計し実行していくプロセスを取ります。その目的は、あらゆる手段を用いて求職者にアプローチし、採用を成功させることです。
一方、採用ブランディングは、そのプロセスの中で「求職者に自社ならではの魅力を印象付ける」という活動です。自社の価値観や魅力を一貫したメッセージやコンテンツで発信することで、求職者の心に信頼と共感を生み出し、ポジティブな企業イメージを定着させる役割を担います。また、求職者の記憶に働きかける行為であるため、企業側で完全にはコントロールができないのがポイントです。
これらを踏まえると、採用マーケティングが「採用を成功させるための採用市場に働きかけるすべての活動」であるのに対し、採用ブランディングはその中で「自社の魅力を求職者の記憶に入り込ませ、良い印象を残し、採用を有利にする活動」と言えます。
なぜ今、採用ブランディングが重要なのか?
採用ブランディングが注目される理由としては、主に以下の3つがあげられます。
- 理由1:労働市場の変化
- 少子高齢化による労働力不足
- 転職の一般化による人材の流動性の高まり
- リモートワークの普及による地理的制約の減少
- 理由2:求職者の価値観の変化
- 仕事に対する価値観の多様化
- SNSからの情報収集の一般化
- 終身雇用への期待の希薄化
- 理由3:採用コストの上昇
- 専門性を持つ人材獲得のための予算投下競争
- 早期離職による採用コストの増大
- 採用チャネルの多様化
これらの理由が絡み合い、「企業が人を選ぶ時代」から「人が企業を選ぶ時代」へと大きく変化しています。したがって、採用ブランディングのような「選ばれるための創意工夫」をしなければ、膨大なコストがかかり続けるだけでなく、自社が欲しい人材の確保も難しい、というのが多くの企業が直面している現状です。
4つのマーケティング理論から学ぶ採用ブランディング
採用ブランディングを体系的に分かりやすく捉えるために、マーケティングやブランディングでよく使われる理論をいくつかピックアップし、あてはめて考えてみましょう。ここでは、以下の4つの理論を紹介します。
- ポジショニング
- 顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)
- PESO
- コンテンツマーケティング
1. ポジショニング
マーケティングでよく使われる理論にSTPという考え方があります。Sはセグメンテーション、Tはターゲティング、Pはポジショニングの頭文字を取った言葉です。つまり、市場をある一定のルールで区切り、その中で自社のターゲットを明確にし、そのターゲットにとってのポジションを決める、という考え方になります。
このうち、ポジショニングは「顧客にとって、自社商品をどのような位置づけにするか」を決める行為であるため、ブランディングとの関わり合いが非常に強いです。これを採用に置き換えると、採用ブランディングにおけるポジショニングとは、「求職者にとって、他社と比べて自社をどのような印象に位置づけるか」ということを指します。
したがって、ポジショニングとは“差別化戦略”そのものともいえます。数ある企業の中で、自社がどのように見られたいか、どのように印象づけたいかを明確にすることで、求職者に想起されやすくなり、好印象を持たれやすくなる、まさに採用ブランディングの軸となる考え方です。
ポジショニングを行う際は、求職者の行動に影響する3つの異なる側面から、自社がどのような位置づけにあるのかを明確にしていくことも多いです。
- 1. 機能ベネフィット:実利的な価値
- 給与が高い
- スキルアップできる
- 福利厚生が充実している
- 環境が整備されている
- リモートワークができる
- 2. 情緒ベネフィット:感情的な価値
- 楽しそう
- やりがいがありそう
- ワクワクする
- 安心して働けそう
- 人間関係が穏やかそう
- 3. 自己表現ベネフィット:象徴的な価値
- この会社で働けたら、誇りに思える
- この会社で働いたら、家族や友人に自慢できそう
- この会社で働くことに、キャリアや人生の意義を感じる
これらの要素を組み合わせることで、自社の特徴を多面的に示すことができます。自社と他社の位置づけを明確にし、自社ならではの差別化された価値を探っていきましょう。
2. 顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)
ポジショニングで打ち出した企業の魅力は、求職者が実際に体験することでより深く、明確に伝わります。採用ブランディングで成果を出すには、企業が自社のベネフィットを打ち出すだけでなく、その魅力を、選考プロセス全体の「体験」を介して、求職者に感じてもらうことが重要です。
ここで参考になるのが、マーケティングで使われる「顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)」の考え方です。顧客体験とは、顧客が商品やサービスに触れるすべての接点で得る体験を指します。
採用に当てはめると、これは求職者が企業情報に触れたり、説明会や面接を体験したりする過程で得る印象や感情を指します。この体験が積み重なることで、求職者にとっての企業のイメージや魅力が形作られていきます。
つまり、候補者体験は単なる応募プロセスではなく、「求職者に企業の価値や魅力を印象づける体験設計」として捉えることが重要です。このような体験を体系的に管理することで、ポジショニングで打ち出した企業の差別化ポイントが求職者の記憶にしっかりと定着し、企業イメージとして強化されていきます。
候補者体験の5つのステップ
- 1. 認知段階:企業を知る
- 求人サイト、SNS、ロコミサイトでの情報収集
- 2. 関心段階:詳しく調べる
- 企業サイト、採用サイトの閲覧
- 説明会への参加
- 3. 応募段階:実際にエントリーする
- 応募フォームへの応募
- 応募後の連絡
- 4. 選考段階:面接・試験を進める
- 面接体験
- 選考課題
- 5. 意思決定段階:入社を決める
- オファー面談
- 入社手続き
このように候補者体験を設計・管理することで、単なる情報提供ではなく、体験を通じて求職者の印象を形成する採用ブランディングにつなげることができます。
3. PESO
マーケティングにおいては「PESO」という考え方があります。これは、自社の情報発信を有料・獲得・共有・自社メディアの4種類に分類し、それぞれを連携させて効果的に活用する手法で、採用ブランディングにも応用できます。
具体的には、PESOはそれぞれ以下の頭文字を指しています。
- ペイドメディア(Paid Media):有料メディア
- アーンドメディア(Earned Media):獲得メディア
- シェアードメディア(Shared Media):共有メディア
- オウンドメディア(Owned Media):自社メディア
採用マーケティングにおけるPESOは、以下となります。
- P (Paid Media):広告費を支払って掲載してもらう
- 求人媒体(Indeed 、リクナビ、マイナビなど)
- SNS広告(LinkedIn、Facebook、Instagramなど)
- 紙媒体広告(新聞、タウンワークなど)
- 動画広告(YouTube、タクシー広告など)
- E (Earned Media):第三者から取り上げられる
- メディアでの紹介
- 業界紙での紹介
- S (Shared Media):SNSなどで共有され拡散される
- SNSの投稿(X、Facebook、Instagramなど)
- SNS上でのクチコミ
- インフルエンサーの紹介
- O (Owned Media) :自社が運営するメディア
- 採用サイト
- 企業ブログ
- YouTubeチャンネル
- メルマガ
これらのメディアを横断的に連携させることで、広範囲の求職者に対して、一貫したメッセージを届け、応募や関心につなげられます。特にオウンドメディアは、自社でコントロールできる発信元、情報を整理・蓄積し、長期的な採用ブランディングに活用できます。
オウンドメディアを始めたいけれど、始め方がわからないという方は、「採用オウンドメディアとは?成功事例11選と始め方、効果を徹底解説」の記事も参考にしてみてください。
4. コンテンツマーケティング
採用ブランディングでは、求職者に自社の魅力や価値を多角的に伝え、好印象を持ってもらうことが重要です。その手段のひとつが、コンテンツマーケティングです。特に、PESOでも紹介したオウンドメディアでの発信が、コンテンツマーケティングではよく使われます。
コンテンツマーケティングとは、価値のある情報やコンテンツを継続的に発信することで、顧客との関係を築く手法です。採用においては、求職者にとって有益な情報を発信することで、自社への関心を高め、関係性を構築し、結果として採用ブランディングを強化することにつながります。
効果的な採用コンテンツの例
- 従業員インタビュー動画
- 実際の働き方やキャリア体験談
- 入社理由や仕事のやりがい
- 職場環境の紹介
- オフィスツアー動画
- 1日の業務の流れ
- 社内イベントの様子
- 専門的な情報発信
- 業界動向の分析記事
- 技術的な知見の共有
- キャリア開発のアドバイス
- 教育的コンテンツ
- スキルアップのためのセミナー動画
- 業界に関する基礎知識
- 面接対策やキャリア相談
これらのコンテンツを継続的に発信することで、求職者は企業の仕事や社風、キャリアビジョンを具体的に理解できます。その結果、応募前の関心や信頼が高まり、実際の応募や説明会への参加、資料請求などの行動につながりやすくなります。
採用ブランディングの効果測定
採用ブランディングは、成果が見えづらいと言われがちです。理由としては、求職者の印象や関心、企業イメージの変化といった定性的な要素が大きく影響するため、応募数や内定承諾率などの定量指標だけでは把握しにくいことがあげられます。
また、ブランディング施策は即効性があるものばかりではなく、効果が表れるまでに一定の時間を要します。一般的には、認知や印象の変化が見え始めるまで3〜6か月程度、応募数や内定承諾率など行動面での効果が実感できるまでには、少なくとも1年はかかるケースが多いです。これは、求職者が複数の情報接点を通じて企業を理解・比較し、意思決定に至るまでに時間を要するためです。
したがって、すぐに成果を出すことを目指すよりも、中長期的なモニタリングと改善のサイクルを前提にした効果測定が重要です。定量データと定性データを組み合わせ、継続的に変化を追うことで、施策の成果を正確に捉えられます。
主な指標としては、以下の2つをおすすめします。
- 1. 行動の定量測定:ブランディングが求職者の行動変化につながっているかの評価ができる
- 応募者数の変化
- 応募者の質の変化(通過率、定着率)
- 採用サイトの閲覧数や滞在時間の変化
- 説明会の参加者数や満足度
- 2. 結果の定量測定:採用活動全体にどのくらい寄与しているかの確認ができる
- 内定承諾率
- 1人あたりの採用コスト
- 採用工数の短縮
- 新入社員の定着率
- 社員のエンゲージメントスコア
もし、もう少し定性的なエビデンスも観測したい場合には、以下も指標として扱うことができます。
- 3. 認知度の定量測定:求職者にどれだけ自社を認知してもらえるかの把握ができる
- 認知度アンケートの結果
- 検索エンジンでの企業名での検索数
- SNSでの企業名の言及数
- 4. 印象の定性測定:認知度だけでなく、自社の印象がどう伝わっているかの確認ができる
- 企業イメージのアンケートの結果(革新性、安定性、成長性)
- クチコミによる評価スコア
- SNSでの言及内容の傾向
これらの指標を組み合わせ、仮説と検証を繰り返す形で分析することで、どの施策がどのような影響をもたらしたかを具体的に把握できます。定性・定量の両方を使うことで、単に数字だけで判断する場合に比べて、成果が見えにくいという課題を解消しやすくなります。
採用ブランディングを成功させる3つのポイント
採用ブランディングは、自社の魅力や方針が明確でないと、期待した成果につながらない企業もあります。そこで、以下の3つのポイントを意識することで、より効果的に施策を進め、採用ブランディングを成功に近づけることができます。
1. 自社の魅力を効果的に発信する
採用ブランディングでは、クリエイティブな要素の活用が不可欠です。コピーやビジュアルで印象を工夫することで、求職者に強く訴求することができます。しかし、いくら魅力的なメッセージを発信しても、それが単なる理想像で、実態が伴っていなければ求職者に誤解を与え、入社後のミスマッチや早期離職につながりかねません。
大切なのは、現状の「自社の今ある魅力」を正確に把握し、正直に、そして効果的に求職者に届けることです。背伸びをするのではなく、ありのままの姿を伝えることで、入社後の定着と活躍につながる信頼関係を築くことができます。
2. 継続的に取り組む
採用ブランディングは、短期間で成果がでるものではありません。継続的に取り組むことで、少しずつ浸透して信頼性が強まるものです。一般的には、施策開始から数か月から半年程度で応募者の認知や関心に変化が現れ、少なくとも1年以上続けることでブランドが定着し、応募者の質も向上していきます。
すぐに結果が出ないからと切り捨てず、数年先の長期的なゴールを見据え、「毎週〇〇回発信を行う」などの、行動計画をたてるのがおすすめです。社内のリソース、外部リソース、予算などを見積もって、持続性のある活動方針をたてましょう。
3. 全社を巻き込んだ取り組み(インナーブランディング)
採用ブランディングは、採用担当者だけで完結するものではありません。経営陣、マネージャー、社員全員が関わり、社内外で一貫した価値を伝える必要があります。
この社内向けの取り組みを、インナーブランディングと呼びます。社員向け説明会やガイドライン作成、成功事例の共有などを通じて、社員自身が自社の魅力を理解し、発信に協力できる状態を整えることが必要です。
全社員が共通認識を持ち、魅力を内側から発信することで、対外的なメッセージに説得力と深みが生まれます。
具体的なアクションチェックリスト
次は、具体的な行動に採用ブランディングを落とし込んでいきましょう。1つずつ進めることで、自社の採用ブランディングが確立されていきます。
【STEP1:現状把握】
- 自社の採用ブランディングの現状を把握する
- 競合他社の採用ブランディングを調査する
- 求職者向けアンケートを実施して自社のイメージを把握する
- クチコミサイト(OpenWork、転職会議など)での評価をチェックする
- 採用プロセスを整理し、候補者体験を可視化する
【STEP2:戦略策定】
- 採用ターゲットを明確に定義する(ペルソナ作成)
- 自社のポジショニングを決める
- 競合他社との差別化ポイントを明確にする
- 発信すべきメッセージの軸を決める
- KPI(成果指標)を設定する
【STEP3:クリエイティブ設計】
- 求職者に伝えたいことから、クリエイティブのコンセプトを決める
- クリエイティブのコンセプトをコピーに反映し、他社との違いを明確にする
- クリエイティブのコンセプトをデザインに反映し、他社との違いを明確にする
- クリエイティブのガイドラインを作る、制作物に反映させる
【STEP4:コンテンツ制作】
- 採用サイトを改善する(デザイン、コンテンツ、使いやすさ)
- 従業員インタビュー動画を制作する(最低3名分)
- 職場環境紹介コンテンツを作る
- 代表メッセージ・ビジョンをわかりやすく伝える
- 業務の流れを紹介する
- 福利厚生・制度を整理してわかりやすく説明する
- キャリアパスを可視化する
【STEP5:チャネル展開】
- SNSアカウントを開設・改善する(X、LinkedIn、Instagramなど)
- 求人サイトでの企業ページを充実させる
- YouTubeチャンネルを開設する
- 企業ブログで定期的に情報発信する
- メルマガやニュースレターを配信する
- 業界イベントに参加する
【STEP6:プロセス改善】
- 応募から内定までのプロセスを見直す
- 応募者への連絡を迅速化する(24時間以内返信を目指す)
- 面接官トレーニングを実施する
- 企業説明会の内容を改善する
- オフィス見学の機会を設ける
- 内定者フォローを充実させる
【STEP7:社内体制構築】
- 採用ブランディング責任者を決める
- 全社員向けに採用ブランディングの重要性を説明する
- 従業員にSNS発信のガイドラインを作成する
- 管理職向けに採用面接トレーニングを実施する
- 社内の声を定期的に収集する仕組みを作る
【STEP8:効果測定・改善】
- 月次でKPIをモニタリングする
- 四半期ごとに採用ブランディングの効果を分析する
- 応募者・内定者にフィードバックを求める
- クチコミサイトでの評価を定期的にチェックする
- 競合他社の動向を継続的にウォッチする
- PDCAサイクルを回して改善を続ける
【継続的取り組みのために】
- 採用ブランディングを年間計画に組み込む
- 予算を確保する
- 外部パートナー(制作会社、コンサルタント)との連携を検討する
- 業界トレンドを常にキャッチアップする
- 新しいプラットフォームやツールの活用を検討する
まとめ
優秀な人材に選ばれる企業になるためには、採用ブランディングが不可欠です。この記事で解説した採用ブランディング手法で、自社の魅力を再定義し、求職者へ効果的に伝えましょう。
まずは、上記のチェックリストを活用して、STEP1の現状把握から始めてみてください。小さな一歩でも、継続することで必ず成果につながります。優秀な人材に「この企業で働きたい」と思ってもらえることを目指して、今日から採用ブランディングに取り組んでいきましょう。
また、採用ブランディングにお困りの際には、是非私たちにご相談ください。
私たちは、採用人事戦略から共に考える
採用サイトに強いウェブ制作会社です
採用に精通したコンサルタントたちがお客さまの採用サイトの問題を解決します
こんな記事も読まれています