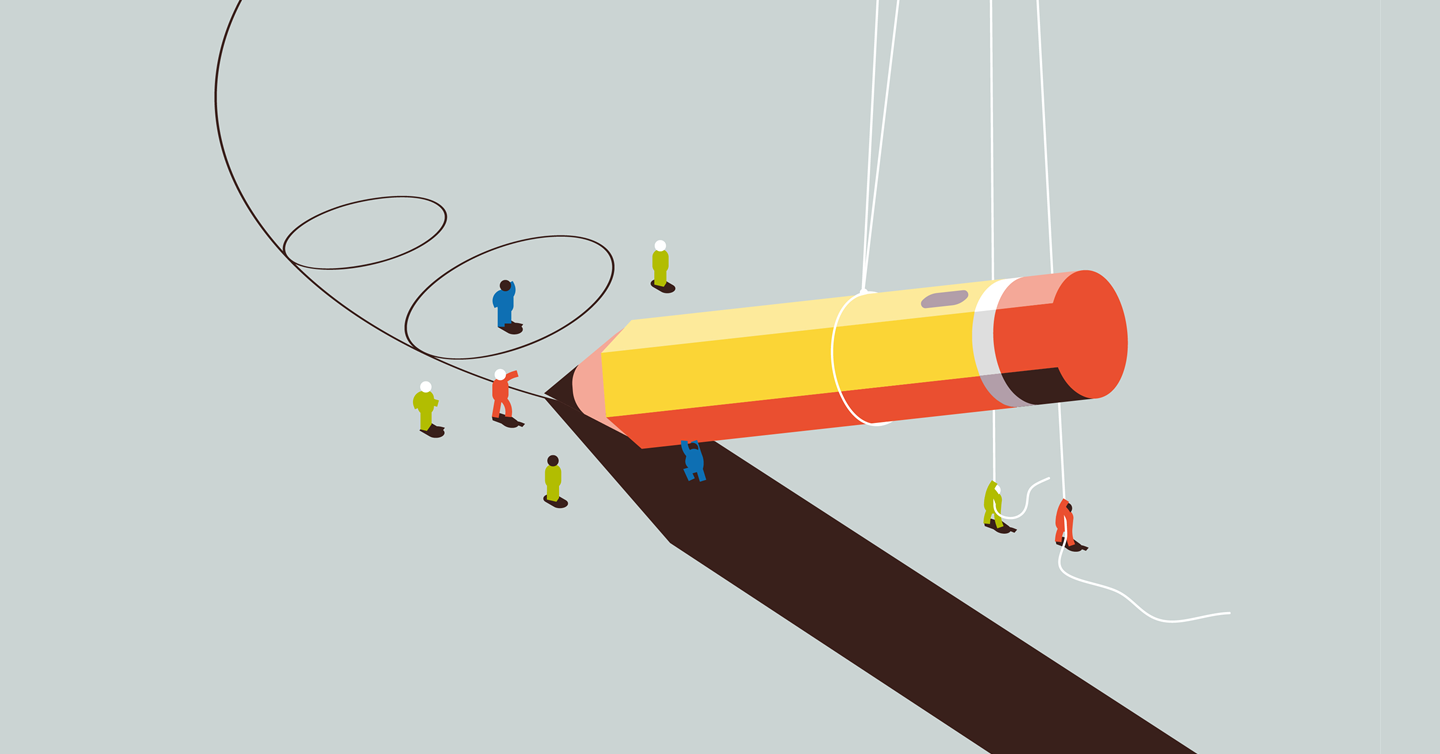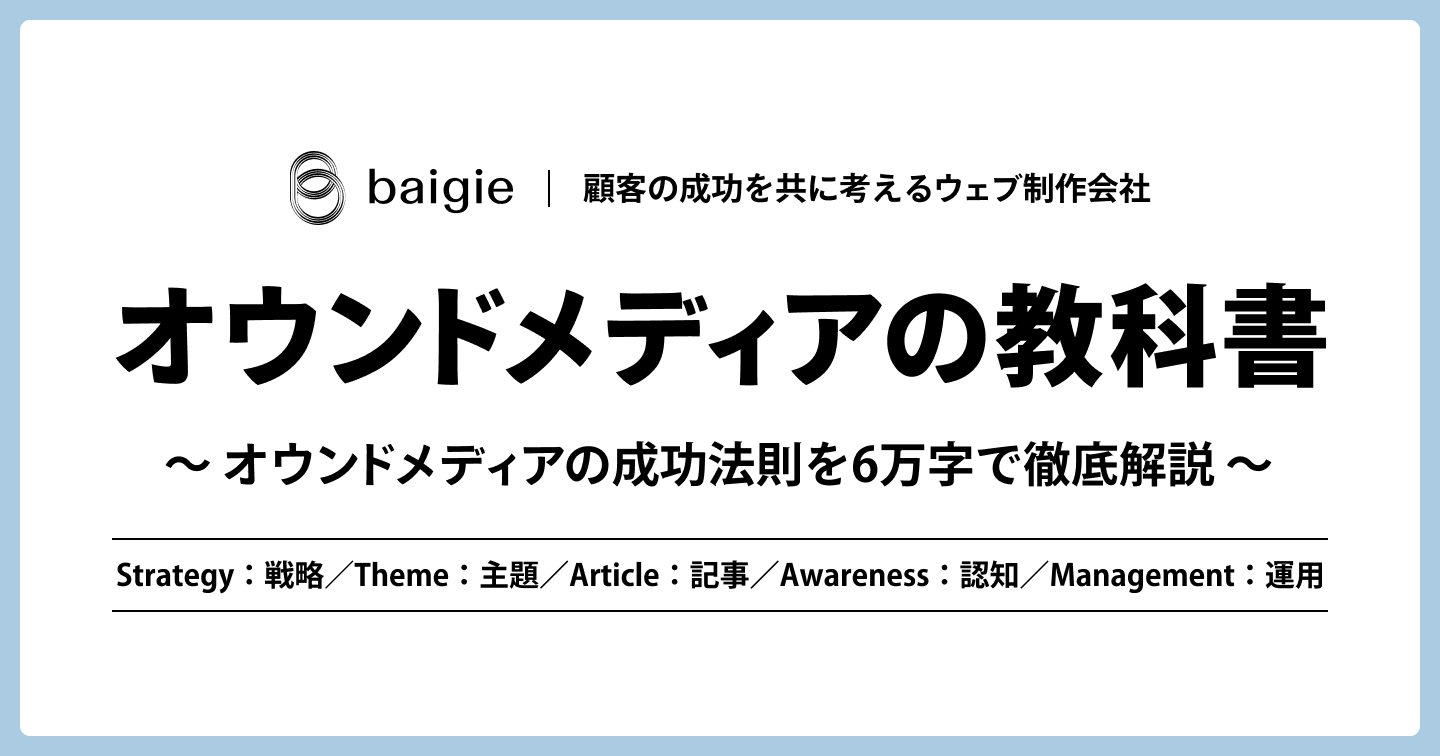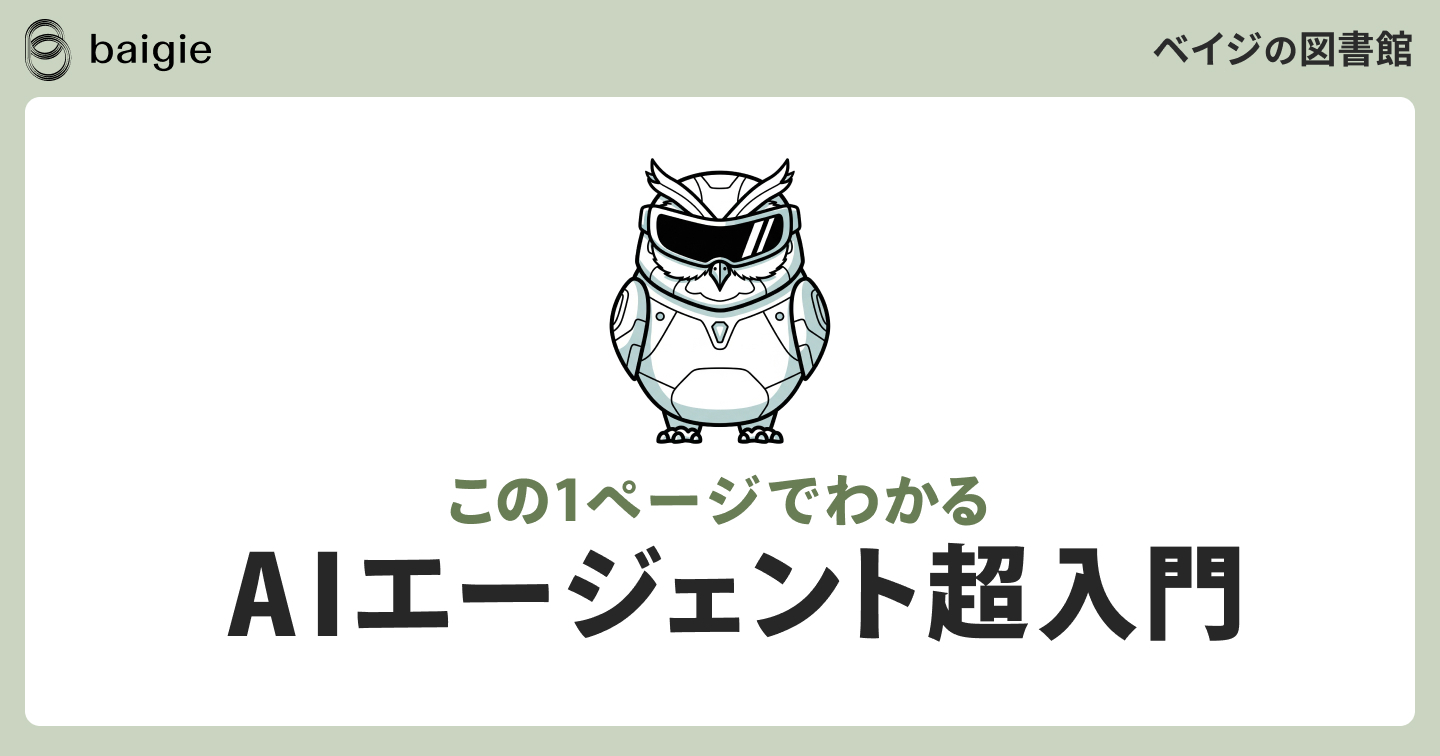AIで「正しい記事」を執筆する完全ガイド|情報の正確性を担保する5つのステップ
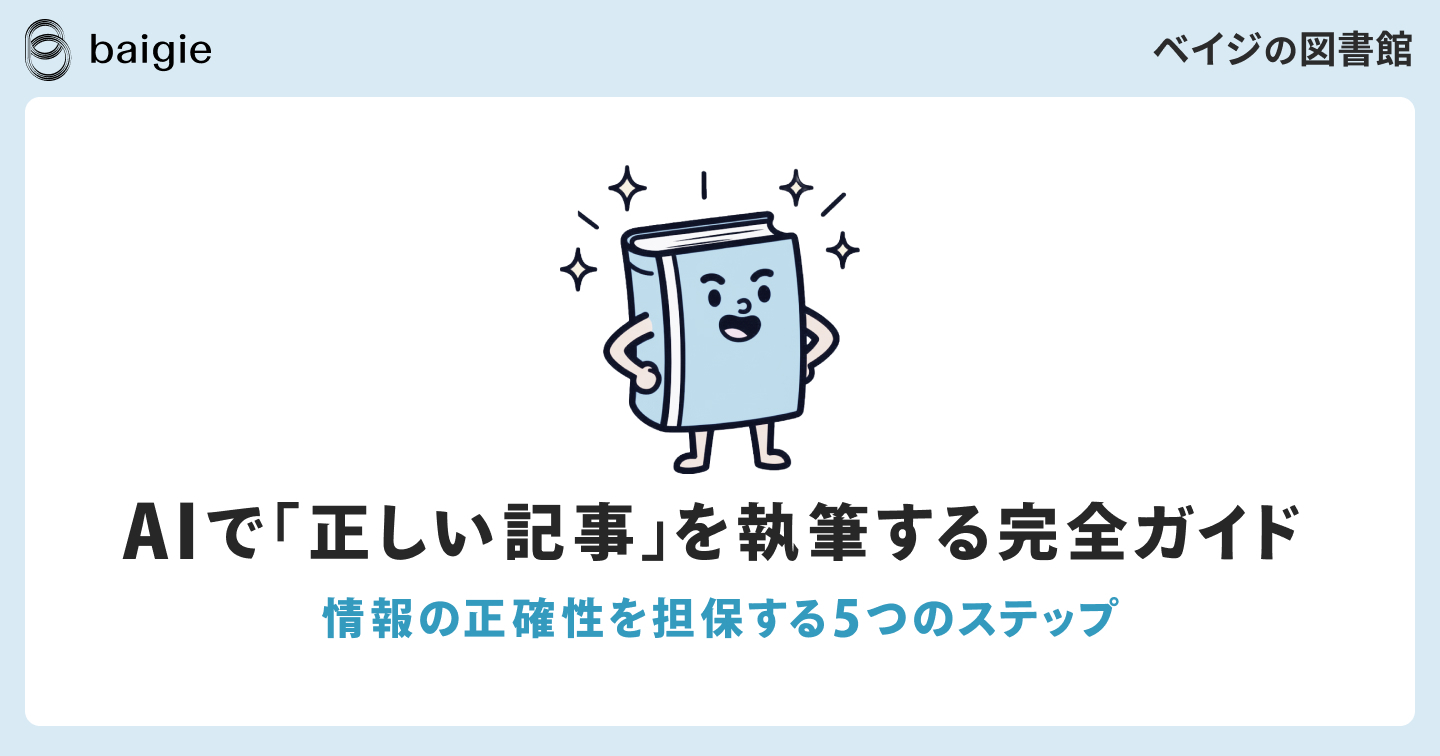
「AIを使えば、ブログ記事が10分で書ける」
数年前まではSFの世界の話だったことが、今や現実のものとなりました。ChatGPT、Gemini、Claudeといった高性能な生成AIの登場は、コンテンツ制作の現場に革命をもたらしています。これまで数時間、あるいは数日かかっていたリサーチや構成案作成、そして記事の執筆といったプロセスが、AIの活用によって劇的に短縮されたことを日々実感しているのではないでしょうか。
この変化は、多くの企業や個人のコンテンツマーケティング、オウンドメディア運営に大きな福音をもたらしました。これまでリソース不足で実現できなかった施策、例えば「毎日コンテンツを更新する」「狙いたいキーワードを網羅した記事を大量に投下する」といった戦略が、現実的な選択肢として視野に入るようになったからです。
しかし、その進化の裏側で、課題も広がりつつあることにも、私たちは目を向ける必要があります。AIによるコンテンツの爆発的な増加は、同時に「質の低いコンテンツの氾濫」という新たな問題を生み出しました。10分で記事の形を作ることはできても、「正しい記事」に仕上げるためには、企画や検証など人の力が今もなお不可欠です。その点を改めて考察していきたいと思います。
目次
「正しい記事」とは |“正しい”だけが文章の価値ではない
「正しい記事」を目指す前に、そもそも完全に「正しい」文章は存在しない、という前提を確認しておきたいと思います。
- 史料が後から更新されれば「事実」は書き換わる
- 文脈や経験、個人の価値観によって「正しさ」の解釈は固定しない
- ときに“正確さ”より“物語性”が読者の心を動かすこともある
一例を挙げれば、詩やエッセイ、小説・広告コピーなどは必ずしも厳密なファクトを要しません。それでも人を励まし、行動を変え、ときには社会をも動かす力を持つことは誰もが納得することでしょう。
そのうえで、この記事で「正しさ」を改めて取り上げるのは、検索や意思決定の拠り所となる情報系コンテンツにおいては、感動や共感だけでなく“事実に裏づいた信頼”を同時に提供する必要があると考えるからです。
その前提を踏まえ、ここでは便宜的に「正しい記事」を次の5 項目で定義します。
この記事における「正しい記事」の定義(5 要素)
| 条件 | 端的な説明 | 主なガイドライン例 |
| 1 正確性 | 一次情報を確認したうえで検証可能 / 誤情報を排除 | Google 検索品質評価ガイドライン、厚労省「医療情報サイトのガイドライン」 |
| 2 独自性 | 調査・経験・視点など“あなたにしか書けない”価値を盛り込む | Google Helpful Content ドキュメント、E-E-A-T「Experience」 |
| 3 読者満足度 | 検索意図や課題を具体的に解決し“役に立つ”体験を提供 | Google Helpful Content/Search Quality 各ガイドライン |
| 4 可読性 | 誰でも理解しやすい構成・表現・UXを整える | Nielsen Norman Group 可読性研究、一般的可読性ガイド |
| 5 倫理性 | 情報源・制作フローを開示し、著作権と訂正責任を明示 | The Trust Project、SPJ Code of Ethics、Google Spam Policy |
この5 つは報道倫理・学術的レポート・ライティングなど、分野を超えて広く共有される基準です。GoogleのE-E-A-Tも、その一部を検索品質評価の文脈で具体化したチェックリストの一つでしかありません。つまり、『E-E-A-Tをすべて満たせばよい』というわけでもなく、『データが違うから即減点される』という単純なものでもありません。記事の目的や読者体験に応じて、“正確さ”と“感動”をどう両立させるかが、この記事で言う「正しい記事」の重要なポイントとなります。
この定義と立ち位置を踏まえ、この記事では
- 正確性 2. 独自性 3. 読者満足度 4. 可読性 5. 倫理性
という実務的な「5 つの条件」に整理・分類し、AI 時代でも量と質を両立させる具体的な手順を解説します。
広がりつつある「AIっぽい記事」への不信感
あなたも、ウェブサイトを閲覧していて、こんな記事に遭遇した経験はないでしょうか?
- どこかで読んだことがあるような、ありきたりで表面的な情報しかない記事
- 日本語として不自然な言い回しや、文脈がおかしい箇所が目立つ文章
- 明らかに事実と異なる、あるいは根拠不明なもっともらしい説明
これらは、いわゆる「AIっぽい記事」の典型的な特徴です。AIが生成した文章を、人間の手による確認や編集を経ずにそのまま公開することで、こうした質の低いコンテンツがインターネット上に増加していることもまた事実です。
Google の評価基準とスパムポリシー
この状況を、検索エンジンの巨人であるGoogleも看過していません。Googleは2025年現在、『AIが生成したか人が書いたか』ではなく、『その内容が読者の役に立つかどうか』を評価基準としています。つまり、 “AI 生成かどうか” ではなく “経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)” を総合評価しているのです。そのため、AIによる自動生成そのものはポリシー違反ではありません。
しかし、2024 年 3 月改訂のスパムポリシーでは 検索順位操作を主目的にした大量生成(Scaled Content Abuse) についてを明確にスパムと定義しました。Googleは公式ドキュメントの中で、「検索トラフィックを獲得することだけを目的とした、過度な自動化(AI)の使用はスパムに関するポリシーの違反(検索順位操作を主目的とする場合)」であるとも明言しています。これは、「AIを使って記事を量産すればSEOで勝てる」などの安易な考え方への明確な警告だと考えていいでしょう。
アップデートの影響も検知されてきている
実際に、このアップデート以降、内容が薄く独自性のないAI生成コンテンツばかりを掲載していたサイトの検索順位が大幅に下落したという報告が、世界中のSEO専門家から多数寄せられています。
もちろん、AIによる記事作成がすべてマイナス評価になるわけではありません。しかし、安易に記事を大量生産する戦略は、サイト全体の評価を下げてしまう可能性があることも意識しておく必要があります。
AIの「ハルシネーション(幻覚)」がもたらすリスクとは
AIライティングのもう一つの問題として「ハルシネーション(幻覚)」があります。ハルシネーションとは、AIが事実にもとづかない情報を、あたかも真実であるかのように生成する現象を指します。
誤情報が招く深刻な影響
AIは、学習した膨大なデータから「それらしい」文章を生成することは得意ですが、「何が事実で、何が嘘か」を本質的に理解しているわけではありません。そのため、平然と嘘の情報を生成してしまうことがあります。例えば、Stanford UniversityのHELM 2024(Holistic Evaluation of Language Models)によると、DisinformationシナリオでのGPT-4の正答率は61%であり、約4割が誤答だったと報告されています。
参考:言語モデルの総合的評価
これらによって、例えば「〇〇という成分には、がんに効く効果がある」といった誤った医療情報や、「△△社の株価は来月2倍になる」といった断定的な投資情報など、読者の生命や財産に深刻な影響を及ぼしかねないデマ情報を生成してしまう可能性があるのです。
このような誤情報を発信してしまえば、読者からの信頼を失うだけでなく、企業のブランドイメージを大きく毀損してしまうでしょう。場合によっては法的な責任を問われる事態にまで発展するかもしれません。
YMYL 領域で徹底すべき対策
ハルシネーションは、検索エンジン対策でなくても、すべてのカテゴリ、業界で配慮しなければなりません。特に医療・金融など YMYL 領域では注意する必要があります。なぜなら誤情報の影響が大きくなりがちだからです。GoogleもYMYL領域に特に注視していることを考え合わせると、厚生労働省ガイドラインや学会指針を参照しながら以下を徹底し、人の目を通すことが必要でしょう。
- 専門家レビュー:医療系なら医師、金融系なら有資格者が必ず監修
- 一次情報へのリンク明示:公的機関・査読済み論文・公式統計など
- 更新日・最終確認者を表記:情報鮮度と責任所在を明確化
AI時代の「正しい記事」5つの絶対条件
ではここで、先ほど定義した「正しい記事の5つの絶対条件を、さらに具体的に整理してみましょう。
【条件1:正確性】信頼の土台となる情報の正確性
第1の条件は、何よりもまず「正確性」です。記事に含まれる情報が、事実にもとづき、客観的な裏付けがとれていること。これは、読者との信頼関係を築くうえでの大前提となります。
前述の通り、AIは「ハルシネーション」により誤った情報を生成するリスクを常に抱えています。統計データ、歴史的な事実、専門的な知見、法律や制度に関する情報など、正確性が求められる記述については、AIの出力を鵜呑みにすることは絶対に許されません。
信頼できる情報源(官公庁の発表、学術論文、専門機関のレポート、報道機関の一次情報など)を人が必ず確認し、情報の裏付けを取る「ファクトチェック」というプロセスが不可欠です。この地道な作業を怠ると、記事は信頼性を失い、単なる「情報のゴミ」と化してしまう危険があります。
【条件2:独自性】自分にしか書けない価値を加える
第2の条件は「独自性」です。AIは、既存の情報を学習し、それを再構成して文章を生成します。そのため、AIが生成したままの文章は、どうしても「どこかで読んだことがあるような、ありきたりな内容」になりがちです。
Googleが重視しているのも、この独自性です。他のサイトの情報をまとめただけの内容では、読者にとって新たな価値を提供しているとは言えないからです。「正しい記事」には、その書き手(あるいはメディア)ならではの価値が必ず含まれています。それは、以下のような要素によって生まれます。
- 一次情報: 独自の調査、インタビュー、アンケート結果など。
- 経験や知見: 筆者自身の体験談、成功・失敗事例、長年の経験で培った専門的な考察。
- 独自の切り口: ありふれたテーマであっても、独自の視点から分析し、新たな気づきを与える。
AIにリサーチやドラフト作成を手伝わせつつ、最終的にこれらの「人間ならではの価値」をいかにして記事に吹き込むか。それが、AI時代のコンテンツ制作者の腕の見せどころでもあるのです。
【条件3:読者満足度】「真のニーズ」を見つける
第3の条件は「読者満足度」です。読者が本当に知りたいことは何か? その悩みや疑問を解決し、期待を上回る答えを提供できているか? これが読者満足度、いわゆるユーザーニーズと呼ばれるものです。
例えば、「テレワーク 集中できない」というキーワードで検索する読者は、単に「集中する方法」を知りたいだけではないかもしれません。その心の奥には、「集中できない自分はダメなのではないかという不安」や、「周りの同僚はどうしているのだろうかという孤独感」といった、より深い感情(インサイト)が隠れている可能性があります。
「正しい記事」は、こうした検索キーワードの裏側にある「真のニーズ」までを深く洞察し、読者の心に寄り添い、共感を示しながら、具体的な解決策を提示しなければなりません。AIは検索意図やユーザーニーズの分析は手伝ってくれますが、読者の感情の機微を汲み取ることはできません。そこを踏まえて言葉を尽すのは人の役割です。
【条件4:可読性】AIらしい文章を「伝わる言葉」に変える
第4の条件は「可読性」です。どれだけ有益な情報が書かれていても、読みにくい文章では読者の心に届きません。AIが生成する文章は、文法的には正しくても、無機質で人間味に欠け、読者を惹きつける魅力に欠けることが少なくありません。「正しい記事」は、読者がストレスなくスムーズに読み進められるように、細部まで配慮されています。
- 専門用語は避け、平易な言葉で説明されているか。
- 一文が長すぎず、リズミカルに読めるか。
- 比喩や具体例を用いて、イメージしやすく工夫されているか。
- 会話調を取り入れたり、読者に語りかけたりして、親しみやすさを演出できているか。
AIが生成したドラフトを、生きた人間の言葉へと磨き上げる行為。この編集やリライトのプロセスが、記事の「読後感」を大きく左右します。
【条件5:倫理性】著作権と透明性を確保し、誠実なメディア運営を
最後の条件は「倫理性」です。AIライティングは、著作権やプライバシーといった倫理的な課題と隣り合わせです。
AIは、学習データに含まれる著作物を意図せず複製してしまう可能性があります。生成された文章が、他のウェブサイトのコンテンツと酷似していないか、専用のツールを使って確認する「コピペチェック」は、メディア運営者としての最低限の義務です。
また、読者に対する誠実さの観点から、「AIをどのように活用しているか」についての透明性を確保することも重要でしょう。最近では、記事の末尾にAI利用に関するポリシーを明記するなど、読者との信頼関係を損なわないための配慮も求められ始めています。
このように、これら5つの条件、「正確性」「独自性」「読者満足度」「可読性」「倫理性」を満たして初めて、AI時代の「正しい記事」は完成すると言えます。
「正しい記事」制作全ステップ①:企画・構成
AIライティングと聞くと、多くの人は「文章を生成する」プロセスに注目しがちです。しかし、本当に「正しい記事」を作成するための第一歩は、AIに触れる前の「企画・構成」段階にあります。この設計工程を人間がどれだけ深く考え、主導権を握れるかが、記事の価値を決定づけます。
なぜなら、この段階で「誰に、何を、どのように伝えるか」という記事の骨格、すなわち「正しさの設計図」が作られるからです。この設計図なしにAIに執筆を依頼するのは、地図も持たず出かけるようなもの。どこに辿り着くかわからなければ、予想した目的地に到達することは難しいでしょう。
1.ターゲット読者(ペルソナ)を解像度高く設定する
「正しい記事」は、特定の誰かに向けた手紙のようなものです。不特定多数に向けられた当たり障りのないメッセージは、誰の心にも響きません。そこで重要になるのが「ペルソナ設定」です。
ペルソナとは、記事の理想的な読者像を、一人の架空の人物として具体的に設定したものです。
- なぜペルソナが必要か?
- メッセージが鋭くなる:「みんな」ではなく「あなた」に語りかけることで、記事の訴求力が高まります。
- 内容のズレがなくなる:「この記事はペルソナの悩みを解決できるか?」という明確な判断基準が生まれます。
- 共感を生む: 読者が「これは自分のための記事だ」と感じ、信頼関係が生まれやすくなります。
- ペルソナ設定の項目例
- 基本情報: 氏名、年齢、性別、職業、居住地、年収
- ライフスタイル: 家族構成、趣味、休日の過ごし方、よく見るメディア
- 仕事・課題: 役職、業務内容、抱えている課題や悩み、目標
- 情報収集: どのようなキーワードで検索するか、どんなSNSを使っているか
これらの項目を埋めることで、読者の姿をリアルに思い浮かべやすくなるでしょう。この「たった一人」に向けて記事を書く意識を持つことが、読者が望む「正しいコンテンツ」を生み出す第一歩になります。
2.「読者の悩みと願望」を読み解く
特にSEOにおいては、ペルソナが検索窓に打ち込む「キーワード」は読者の悩みや願望が凝縮された重要な要素です。SEOでなくても、書くべき記事のテーマにおける読者の「検索意図」やそこに隠された「悩み」をどれだけ深く理解できるかが、読者満足度を決定づけます。
検索意図は、大きく4つのタイプに分類できます。
Know(知りたい): 「〇〇とは?」のように、情報を求める意図。
- キーワード例:「AIライティング とは」
Go(行きたい): 特定のサイトや場所に行きたい意図。
- キーワード例:「ChatGPT ログイン」
Do(やりたい): 何かをしたい、購入したいという行動の意図。
- キーワード例:「AIライティングツール おすすめ」
Buy(買いたい): Doの中でも特に購買意欲が高い意図。
- キーワード例:「(特定のAIツール名) 料金」
「正しい記事」を作るためには、作成する記事がどの意図に属するかを見極め、それに最適な答えを用意する必要があります。「Know」の意図を持つ読者に商品を売り込んでも響きませんし、「Do」の意図を持つ読者に概念的な説明だけをしても満足させられません。
さらに「なぜその悩みを持っているのか?」という背景にまで想像力を働かせることで、読者の真のニーズを理解することができるでしょう。
3.競合分析:上位記事から学ぶべきこと、差別化すべきこと
あなたの記事が公開されるウェブの世界には、すでに無数の競合記事が存在します。それらの記事を分析することは、「正しさ」を追求するうえで欠かせないプロセスです。
まず、狙うキーワードやテーマで実際に検索してみて、上位10記事ほどを分析します。分析すべきポイントは以下の通りです。
- 学ぶべき点(共通項):
- 上位記事が共通して取り上げているトピックは何か?(これは読者が最低限求めている情報である可能性が高い)
- どのような構成で書かれているか?
- タイトルや見出しにどのような言葉が使われているか?
- 差別化すべき点(独自性):
- 上位記事が見落としている視点や、情報が不足している部分はないか?
- より新しい情報や、深い考察を加えることはできないか?
- 自身の経験や専門知識を加えられるポイントはどこか?
競合分析の目的は、SEOで上位を狙ったり、単に真似をすることではありません。読者がすでに得られる情報(期待値)を理解したうえで、それを超える独自の価値(満足度)を提供するためにどうすればよいか戦略を立てることです。これが、Googleが評価する「独自性のある、正しい記事」にもつながります。
4.読者を導く「論理的な構成案」を組み立てる
ペルソナ、検索意図、競合分析で得た情報をもとに、いよいよ記事の設計図である「構成案」を作成します。構成案とは、記事全体の流れを見出し(H2、H3)レベルで組み立てたものです。
- 正しい構成案のポイント:
- 導入(リード文): 読者の共感を呼び、この記事を読むことで何が得られるのか(ベネフィット)を明確に提示する。
- 本文: 結論(最も伝えたいこと)から先に述べ、その後に理由や具体例を展開する(PREP法など)。見出しは読者が次に何が書かれているか予測できるような、具体的で魅力的なものにする。
- まとめ: 記事全体の要点を簡潔に振り返り、読者が次に取るべき行動(CTA: Call to Action)を促す。
この構成案をしっかりと作り込むことで、記事全体の論理的な一貫性が保たれ、読者を迷わせることなくスムーズに結論まで導くことができます。AIに執筆を依頼する際も、この詳細な構成案を渡すことで、意図から外れた文章が生成されるのを防ぐことができます。
「正しい記事」制作全ステップ②:ドラフト作成
キーワードやペルソナを決め、構成案を作れたらいよいよドラフトの作成です。
1.目的別に適切な生成AIを選ぶ
構成案が完成したら、いよいよAIツールを使ってドラフトを作成します。現在、主要なAIツールにはそれぞれ特徴と性格があります。どのツールが絶対的に優れているというより、目的に応じて使い分けることが「正しい」活用法です。
- ChatGPT (OpenAI): 対話形式での深掘りや、アイデアの壁打ちが得意。要素整理や分析する能力に長けている。
- Gemini (Google): Google検索と連携しており、最新情報やウェブ上の情報にもとづいた回答の正確性に強みを持つ。
- Claude (Anthropic): 長文の読解・生成能力が高い。誠実で安全性の高い回答を返すように設計されており、倫理的な配慮が必要なテーマに向いているとされる。
自分にとって納得しやすい文体や構成で出力されるかどうかも重要です。一般的な評価だけでなく、自分自身の『使いやすさ』や『修正のしやすさ』なども考慮しましょう。まずは無料で使える範囲でいくつか試し、自分の目的やスタイルに合ったツールを見つけることをお勧めします。
2.リード文を生成するプロンプト例
リード文は、読者が記事を読み進めるかどうかを決める最も重要な部分です。さらに、記事内容のアウトラインでもあります。これをAIに生成してもらえば、どのような記事にすべきかの要素を客観的に整理することも可能になります。これはリライトなどの際にも有効です。
【プロンプト例:リード】
#依頼内容
あなたはプロのWebライターです。以下の情報をもとに、読者の心を掴み、続きを読むメリットが明確に伝わるブログ記事の導入文を3パターン作成してください。
# 記事のテーマ
AIライティングで「正しい記事」を作成するための具体的な方法
# ペルソナ
* 氏名:田中 誠
* 年齢:32歳
* 職業:中小企業でWebマーケティングを担当して2年目
* 悩み:「AIで記事作成を始めたが、内容が薄く、Googleからの評価も低い気がする。情報の正確性や著作権も不安。どうすれば信頼される記事を作れるのか知りたい」
# 読者がこの記事を読むメリット
* AI記事の品質を劇的に向上させる具体的な5つのステップがわかる
* 情報の正確性と倫理性を担保する方法が学べる
* 読者とGoogleの両方から評価される記事作成の自信がつく
3.各見出しの本文を効率的に生成させるプロンプト例
構成案に沿って、各見出しの本文をAIに生成させていきます。ここでのコツは、一度に全文を書かせようとせず、見出しごとに区切って依頼することです。これにより、AIの出力が安定するだけでなく、方向性の違いのあぶり出しや修正も容易になります。
【プロンプト例:見出しごとの本文作成】
# 依頼内容
あなたはITやAI専門の解説者です。以下の構成案の一部である「【条件1:正確性】情報の正しさが信頼の土台」について、ブログ記事の本文を作成してください。
# 前提情報
* 記事全体のテーマ:AIで「正しい記事」を執筆する方法
* ペルソナ:企業のWeb担当者で、AI記事の信頼性に不安を感じている。
* この見出しで伝えたいこと:
* 記事の信頼性は、情報の正確性にかかっていること。
* AIの「ハルシネーション」というリスクを具体的に説明すること。
* 信頼できる情報源の例を挙げ、ファクトチェックの重要性を強調すること。
* 専門用語は避け、初心者にも理解できるように平易な言葉で解説してください。
このように、背景情報や「何を書いてほしいか」を具体的に指示することで、意図に沿った「正しい」ドラフトが生成されやすくなります。
4.AIとの「壁打ち」でアイデアを深める
AIは、文章を生成するだけでなく、思考を深めるための「壁打ち相手」としても非常に有能です。独自性を強めるために使わない手はありません。
- 別の視点を求める: 「このテーマについて、他にどんな切り口が考えられますか?」
- 反論をさせる: 「私のこの意見に対して、批判的な視点から反論してください」
- 具体例を挙げさせる: 「この概念について、初心者にもわかるような具体例を3つ挙げてください」
こうした対話を通じて、自分一人では思いつかなかったアイデアや、論理の穴を発見することができます。これもまた、AIの「正しい」活用法の一つです。
5.AIが生成した文章の「クセ」を見抜いて修正する
AIが生成した文章には、特有の「クセ」があります。これらを理解しておくことで、編集・リライトの際に修正すべき点が明確になります。一例を挙げてみましょう。
- 過度に丁寧、あるいは断定的: 「〜と言えるでしょう」「〜なのは間違いありません」など、不自然な断定や丁寧表現が多い。
- 同じ接続詞の多用: 「また」「さらに」「そして」などが繰り返される。
- 抽象的な表現: 具体例に乏しく、「多くの人々」「様々な方法」といった曖昧な表現に終始する。
- 無感情・無機質: 書き手の熱意や感情が感じられず、教科書のような淡々とした文章になる。
- 壮大・大げさな表現:反対にまるで映画のキャッチコピーのような大げさな表現で物語性をつけようとする。
これらの「AIっぽさ」を人間の手で修正していくことが、次のステップに向けて重要になります。
「正しい記事」制作全ステップ③:ファクトチェック
AIが生成したドラフトは、あくまで「下書き」です。特に、その内容の「正しさ」については一切の保証がありません。この章で解説するファクトチェックは、AIで記事を執筆するうえで、絶対に省略してはならない、最も重要なプロセスです。
これを怠ることは、トラブルのリスクを抱えたまま記事を公開するのと同じです。誤った情報を発信すれば、読者の信頼を失い、メディアのブランドを傷つけ、ときには法的責任に発展する危険もあります。特に、読者の健康や財産に影響を与える可能性のある YMYL 領域では、ファクトチェックの責任は極めて重いと考えるべきです。
1.AIの回答を鵜呑みにせず、すべての情報を「疑う」
ファクトチェックの第一歩は、「AIの回答はすべて疑う」という意識を持つことです。AIはソースが不明確な情報や、古くなった情報、あるいは全くの嘘(ハルシネーション)を、あたかも正しい情報のように混ぜ込んで作成するからです。
ハルシネーションの具体例:
- 存在しない法律や判例を引用する。
- 歴史上の人物の発言を捏造する。
- 科学的に証明されていない効果を、あたかも事実のように語る。
- 架空の統計データや数値を提示する。
これらの情報を見抜くためには、記事に含まれるすべての「事実情報(客観的に検証可能な情報)」に対して、「その根拠(ソース)は何か?」と自問自答する習慣をつけるようにしましょう。
2.ファクトチェックの具体的な手順
具体的なファクトチェックは、以下の手順で進めます。
- 検証対象の洗い出し: 記事の中から、数値データ、固有名詞、専門用語、歴史的事実、法律や制度に関する記述など、客観的な検証が必要な箇所をすべてリストアップします。
- 一次情報(Primary Source)を探す:一次情報とは: 直接的な情報源のこと。官公庁の発表、研究機関の元論文、企業の公式発表(プレスリリース)、法律の条文などが該当します。
- 探し方:官公庁・政府機関の情報:site:go.jp や site:lg.jp をつけて検索します。例:「テレワーク 助成金 site:go.jp」
- 学術論文:Google Scholar, J-STAGE, CiNii などのデータベースで検索します。
- AIのDeep Resarch機能で検索し、提供されたリンク先を目視チェックすることで正確性を測ります。
- 信頼できる二次情報(Secondary Source)で補強する:二次情報とは: 一次情報をもとに、第三者が解説・報道した情報。大手新聞社や通信社のニュース記事、専門家が執筆した解説記事などのことです。個人ブログや信頼性の低いまとめサイトの情報を避け、誰が書いたのか、運営元はどこかが明確な情報源を選びます。同じキーワードやテーマの上位記事をAIで分析し、更新日や参照元などをもとに最新情報をチェックします。
- クロスチェックを行う:一つの情報源だけを信じるのではなく、必ず複数の信頼できる情報源を参照し、内容に矛盾がないかを確認します。情報源によって見解や定義が異なる場合は、その旨を併記するなど、中立的な記述を心がけるようにしましょう。
【参考】ファクトチェックのためのGoogle検索テクニック
ファクトチェックを効率化するためのGoogle検索のコマンドも紹介します。
- “キーワード”:完全一致検索。正確なフレーズを探す際に有効。
- before:YYYY-MM-DD / after:YYYY-MM-DD:期間を指定して検索。最新情報や特定の時期の情報を探す際に便利。
- filetype:pdf:PDFファイルのみを検索。公的機関の報告書や論文を探しやすい。
これらの手順やツールを駆使し、記事の「正確性」という土台をしっかりさせることが、AI時代のコンテンツ制作には必要な配慮です。
「正しい記事」制作全ステップ④:編集・リライト
ファクトチェックを終えたAIのドラフトは、いわば「正確な情報が並んだ文章の素材」です。このままでは、正確なだけで読者の心を動かすには不十分です。正確さは重要な価値ですが、さらにAIにはできない人間ならではの価値を加えることで、初めて本当に『正しい記事』になります。
1.独自性を加えるための5つのアイデア
競合記事との差別化を図り、読者からもGoogleからも「価値がある」と評価されるためには、「あなたにしか書けない情報」を加えることが不可欠です。
- 自身の体験談や失敗談を入れる:
あなたが実際に経験したこと、感じたことは、世界で唯一のオリジナルコンテンツです。一例ですが「私も以前、AIのハルシネーションによって誤った情報を信じてしまい、困った経験があります」というような一文は、読者に強い共感と親近感を抱かせるでしょう。
- 具体的な事例やケーススタディを盛り込む:
抽象的な解説だけでなく、「私のクライアントであるA社では、この方法を導入して、記事作成時間を50%削減しつつ、コンバージョン率を1.2倍に向上させました」といった数字を含む具体的な事例は、記事の説得力を飛躍的に高めます。
- 専門家としての考察や持論を展開する:
単なる情報の羅列ではなく、「これらの事実から、私は今後のAIライティングは『編集者のスキル』が最も重要になると考えています。その理由は3つあります…」のように、あなた自身の専門的な視点からの分析や考えを加えることで、記事の説得力は高まるでしょう。
- 読者への語りかけや問いかけを入れる:
「このような経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか」「このステップは難しく感じるかもしれませんが、まずはここから始めてみることをお勧めします」といった読者への語りかけは、一方的な情報提供ではなく、対話的な雰囲気を生み出し、エンゲージメントの向上につながります。ただし、なんでも問いかければいいわけではありません。使いすぎないよう、全体のバランスにも配慮しましょう。
2.AIっぽさをなくし可読性を高めるには
AIが書いた文章の「クセ」を取り除き、読者が心地よく読み進められるように、表現にも注意しましょう。
- 無機質な表現を人間味のある言葉に: 「〜と言えるでしょう」→「〜だと私は思います」、「〜することが重要です」→「〜することが、成功への近道です」
- 一文を短く、シンプルに: 長く複雑な文章は、読点の位置で分割し、簡潔な文章に直す。
- 比喩や擬人化を活用する: 「ファクトチェックは、いわば記事の『健康診断』のようなものです」
- 専門用語を噛み砕く: 「YMYL」と書くだけでなく、「(読者の健康やお金に大きな影響を与える可能性のある情報のことです)」などと補足説明を入れる。
- 文章のリズムを整える: 同じ語尾(〜です、〜ます)が連続しないように調整する。
「正しい記事」制作全ステップ⑤:倫理と透明性
最後に、AIライティングを行ううえで避けては通れないことは「著作権」の問題もあります。AIが生成した文章は誰のものなのでしょうか?
なお、AI と著作権を巡る法整備は米国・EU・日本の各国でいまだ進行中です。この記事の説明は日本の法律を前提にして説明しています。
1.AI生成コンテンツの著作権についての文化庁の見解
日本の文化庁は、AIと著作権に関する考え方を示しています。その要点は以下の通りです。
- AIが自律的に生成したものは、著作権の対象にならない: 著作権は、人間の「思想又は感情を創作的に表現したもの」に発生します。現状のAIは、人間の創作的な意図を表現するための「道具」と見なされており、AI自体が著作者になることはありません。
- 人間の「創作的寄与」があれば著作物になる可能性がある: 人間がAIを道具として使い、生成プロセスにおいて創作的な意図(プロンプトでの詳細な指示、生成物の選択・修正など)が認められれば、その生成物は人間の著作物として保護される可能性があります。
- 学習データに含まれる著作物の問題: AIは、インターネット上の膨大なデータを学習していますが、その中には著作権で保護されたコンテンツも含まれています。AIがそれらの著作物を意図せず複製(類似)したものを生成してしまうリスクはゼロではありません。
このことから、AIで記事を作成するすべての人間が、生成された文章が他者の著作権を侵害していないかを確認する責任を負うと定義できます。
2.なぜコピペチェックが必要なのか?
他者の著作権を侵害するリスクを回避し、メディアの信頼性を守るために、公開前の「コピペチェック」は必須の作業です。
- 意図しない著作権侵害を防ぐため。
- Googleからコピーコンテンツとしてペナルティを受けるのを避けるため。
- メディアとしての倫理観と信頼性を示すため。
幸い、現在では高精度なコピペチェックツールが数多く提供されています。無料・有料のツールがありますが、法人としてメディアを運営する場合は、より精度の高い有料ツールの導入も検討しましょう。これらのツールは、ウェブ上の膨大なコンテンツと記事を照合し、類似度が高い箇所を指摘してくれます。
3.AI利用を明記すべきか?判断基準と具体的な表記例
最後に、読者に対する「透明性」の問題です。記事の作成にAIを利用したことを、読者に明記すべきでしょうか?
これについては、現行法にAI 利用の明示義務はありません。ただし透明性を重視するメディア姿勢として、以下のようなポリシー表記が推奨されます。
「当記事は人間による企画・編集のもと、一部で生成 AI を補助的に利用しています。最終的な事実確認と編集責任は編集部が負います。」
どのような形であれ、読者に対して誠実であろうとする姿勢が、最終的にメディアの「正しさ」と信頼を築き上げることになるでしょう。
まとめ
ここまで、AIで「正しい記事」を執筆するための具体的な5つのステップ(①設計 → ②生成 → ③検証 → ④仕上げ → ⑤公開)を、具体的な方法論に落とし込んで解説してきました。
最も重要なことは、AIを「全自動の執筆ツール」と考えるのではなく、あくまで「優秀なアシスタント」として位置づけ、人間が常に「正しさ」の主導権を握ることです。
企画・構成で記事の「正しさ」を設計し、AIが生成したドラフトに対して、人間が責任を持ってファクトチェックを行い、独自性を吹き込む。この「AI with 人間」という協業体制こそが、読者とGoogleの双方から信頼されるコンテンツを生み出す唯一の方法です。AIを正しく使えば、コンテンツ制作のプロセスを劇的に効率化しつつ、信頼されるコンテンツを質・量ともに作成することが可能になるでしょう。
私たちは顧客の成功を共に考えるウェブ制作会社です。
ウェブ制作といえば、「納期」や「納品物の品質」に意識を向けがちですが、私たちはその先にある「顧客の成功」をお客さまと共に考えた上で、ウェブ制作を行っています。そのために「戦略フェーズ」と呼ばれるお客さまのビジネスを理解し、共に議論する期間を必ず設けています。
成果にこだわるウェブサイトをお望みの方、ビジネス視点で相談ができるウェブ制作会社がいないとお困りの方は、是非ベイジをご検討ください。
ベイジは業務システム、社内システム、SaaS、管理画面といったウェブアプリケーションのUIデザインにも力を入れています。是非、私たちにご相談ください。
ベイジは通年で採用も行っています。マーケター、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど、さまざまな職種を募集しています。ご興味がある方は採用サイトもご覧ください。
記事カテゴリー
人気記事ランキング
-
デザイナーじゃなくても知っておきたい色と配色の基本 1,417,435 view
-
提案書の書き方~ストーリー・コピー・デザインの基本法則【スライド付】 1,157,221 view
-
簡単CSSアニメーション&デザイン20選(ソースコードと解説付き) 960,175 view
-
【2024年6月版】管理画面のUIデザインにおける25の改善ポイント 590,462 view
-
パワポでやりがちな9の無駄な努力 531,566 view
-
ビジネスに役立つ上手な文章の書き方11のコツ 432,579 view
-
良い上司の条件・悪い上司の条件 375,720 view
-
未経験でも1カ月で即戦力クラスの知識が身に付く『webデザインドリル』公開 369,240 view
-
UIデザインのための心理学:33の法則・原則(実例つき) 352,235 view
-
話が上手な人と下手な人の違い 346,614 view